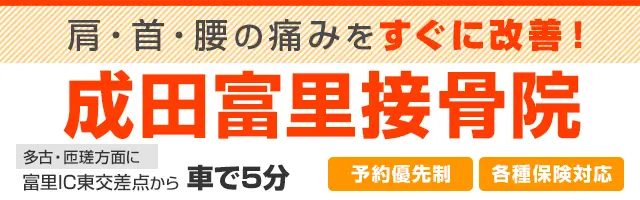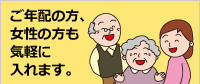オスグッド


こんなお悩みはありませんか?

ジャンプ、ストップ、ダッシュ、キックなど、膝に負担をかける動作が多いスポーツを行っている(例:バスケットボール、サッカー、バレーボール、バドミントン、陸上競技など)
膝のお皿の下に出っ張りが見られ、圧痛を感じる
大腿部(太もも)から膝にかけての筋肉の柔軟性が不足している、下半身の筋肉が硬い
成長期で身長が急激に伸びている
運動後に特に痛みが強くなり、膝下に熱感を感じる
オスグッドについて知っておくべきこと

オスグッド病は、スポーツを行っている学生に多く見られる症状です。そのため、小学生から高校生のお子さんがいる方は、特に注意が必要です。特に小さいお子さんは、痛みを感じる部分を正確に伝えることが難しく、実際の痛みの場所とは異なる場所を抑えてしまうことがあります。そのため、少しでも知識を持つことが非常に重要です。成長痛だからといって放っておくと、後々の影響が出ることがありますので、早期に施術を受けることをおすすめします。
また、成長痛には膝のオスグッド病以外にも、さまざまな部位で発生することがあります。お子さんが痛みを訴えた場合は、早めに検査を受け、適切な施術を行うことが大切です。
症状の現れ方は?

オスグッド病は、小学生から高校生の男子に多く見られる、膝のオーバーユースによる成長痛の一つです。成長期には急激に身長が増えるため、骨も伸びますが、筋肉や腱などの軟部組織は同じようには成長しません。そのため、大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)の柔軟性が低下し、スポーツを行う際にジャンプやダッシュなどの繰り返しの動作によって膝蓋骨(お皿の骨)を引っ張る力が膝下の脛骨粗面という部分に加わります。
成長期の脛骨粗面には、骨が成長するために必要な新しい骨(骨端核)が存在しており、大腿四頭筋の強力な牽引力がその部分に負担をかけ、骨端核の発育が阻害されることがあります。これが、脛骨粗面の突出や痛みを引き起こす原因となります。
その他の原因は?

オスグッド病は、ほとんどが成長期に発症しますが、まれに成人にも発生することがあります。成長期を過ぎ、痛みが緩和された後に再発するケースです。成人になって久しぶりに運動を再開すると、膝に再び強い負荷がかかり、膝下の脛骨粗面が炎症を起こし、以前のような痛みが再発することがあります。このような状態はオスグッド後遺症と呼ばれ、成人であっても油断はできません。
また、スポーツ以外の場面でも、歩くことが多い方や方向転換が頻繁な方は注意が必要です。しかし、圧倒的に多いのは、オーバーユースによる成長障害です。
オスグッドを放置するとどうなる?

捻挫や骨折などの突発的な怪我ではないため、運動を完全に停止する必要はありませんが、痛みがある時は安静にすることが最も重要です。痛みが軽減してきたら、軽い運動から再開します。ただし、強度の高い運動を続けてしまうと、痛みが長引いたり、治りが遅くなったり、成長に影響を与える可能性があります。放置せず、医療機関で適切な検査と施術を受けることをおすすめします。
特に、小学生から高校生の間は身長が急激に伸びる時期です。この時期に適切な処置をしないと、好きなスポーツを長期間行えなくなることがあり、ストレスの原因となるかもしれません。また、完全に治らないまま放置すると、オスグッド後遺症として成人になっても悩み続けることもあります。
当院の施術方法について

オスグッド病は、大腿四頭筋が膝のお皿の下にある脛骨粗面を引っ張ることで炎症や痛みが生じる成長障害です。当院では、大腿四頭筋をはじめ、太ももから膝にかけての筋肉を指圧で柔軟にほぐし、筋膜をストレッチする施術を行っています。筋肉の柔軟性が向上すると、膝にかかる負担が軽減され、痛みの緩和が期待できます。
また、ストレッチは身体全体の柔軟性を高める手技であり、普段伸ばしにくい筋肉にもアプローチ可能です。特にスポーツをしている方にとっては、可動域の拡大がパフォーマンス向上に繋がり、怪我をしにくい身体づくりが期待できます。
改善していく上でのポイント

オスグッド病を施術するうえで大切なことは、頻度とセルフケアです。痛みがある膝や太もも周りの筋肉は非常に硬くなっていますので、ストレッチをしてもすぐに元に戻ってしまうことがあります。そのため、施術の頻度は可能であれば毎日が理想的ですが、最低でも週に2〜3回通院することが推奨されます。繰り返し施術を行うことで、筋肉の柔軟性が徐々に高まり、痛みも落ち着いてきます。
施術はもちろん重要ですが、自宅で行うセルフケアも同じくらい重要です。筋肉の柔軟性は個人差があり、硬くなっている箇所もそれぞれ異なります。当院では、一人一人に合わせたセルフケアのストレッチ方法を指導し、日常的にケアを続けることをサポートします。
監修

成田富里接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:千葉県船橋市
趣味・特技:バレーボール、ボウリング、スノボ、ゴルフ、アニメ